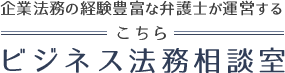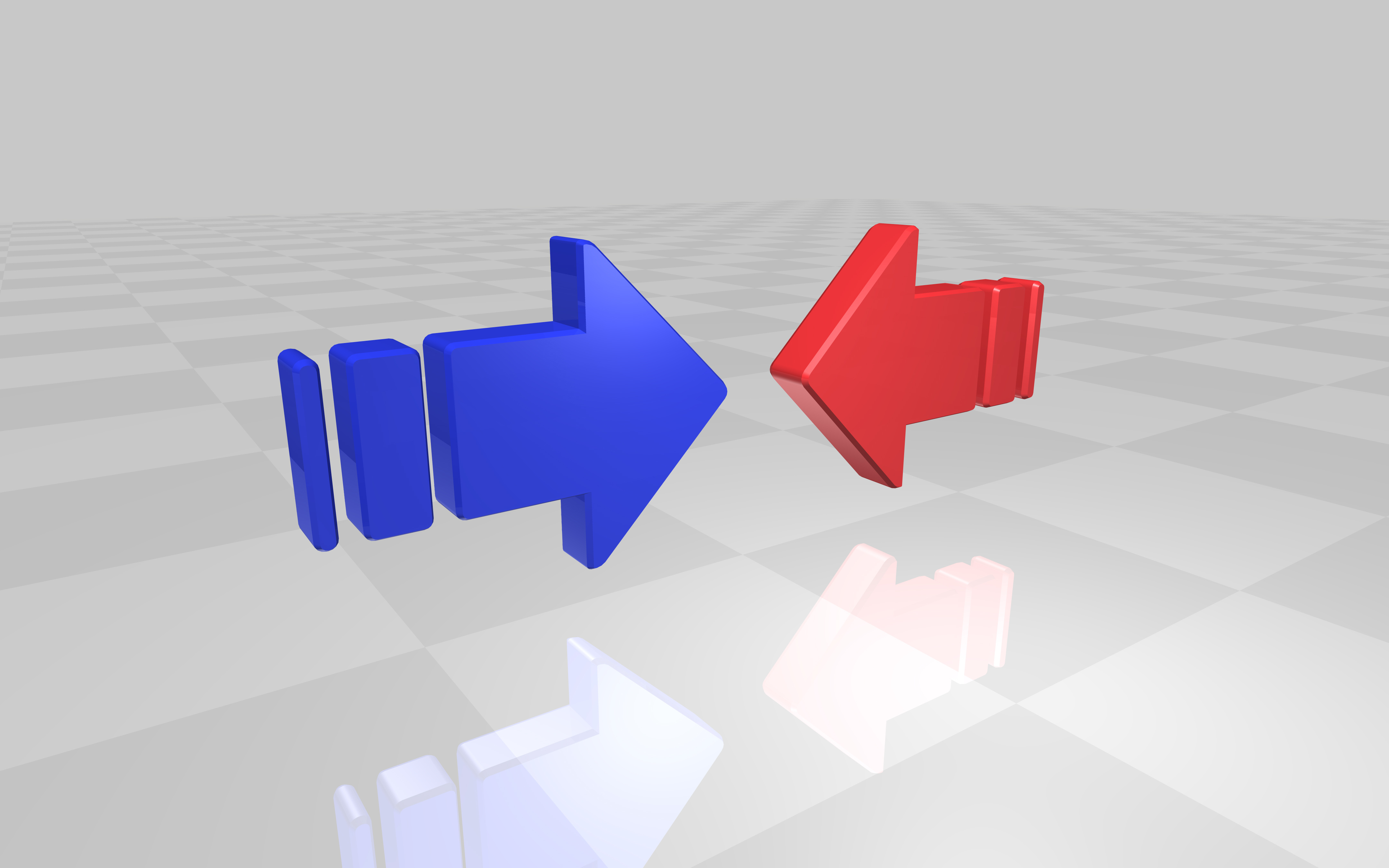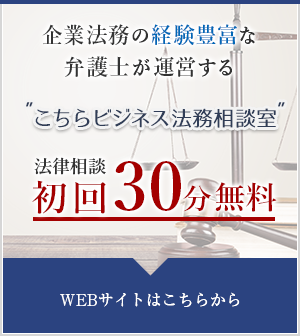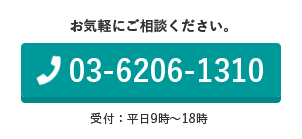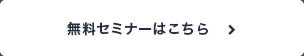取締役や従業員として在任・在職中はもとより、退任・退職後であっても、会社は、あなたが思っている以上に、自社と競合するビジネスを始めたり、同業の会社に就職することに注意を払い、警戒しています。
あなたが何気なく始めたビジネスも、知らず知らずのうちに差止請求や損害賠償請求等の対象となっているかもしれません。もしそれが会社の目に留まれば、会社は、あなたに対する仮処分や訴訟等の法的措置も辞さないでしょう。
このような競業行為に関するトラブルについて、我々がご相談を受けることは多いのですが、会社との間で、競業行為の禁止等に関する合意書や誓約書を作成してしまっているといった理由で負い目を感じ、対応を諦めるほかないと考えている方もいらっしゃるかと思います。
ですが、特に退任・退職後のビジネスは、原則として個人の自由(職業選択の自由)であり、会社が過度に制限をかけてよいものではありません。
そこで、本記事では、どのような場合に競業行為が禁止され、又は許容されるのか、取締役と従業員の場合、さらには在任・在職中と退任・退職後の場合に整理して、分かりやすく解説していきます。
1 取締役の場合
1-1 在任中
1-1-1 在任中の競業行為は、原則として禁止
在職中の取締役に関しては、株主総会の承認(取締役会設置会社の場合には、取締役会の承認)を得なければ、競業行為自体を行うことができません(会社法356条1項1号、365条1項)。
会社法356条1項 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1号 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
会社法365条1項 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
会社法356条1項1号によって禁止される競業行為、すなわち「会社の事業の部類に属する取引」とは、会社の実際に行う事業と市場において取引が競合し、会社と取締役との間に利益衝突をきたす可能性のある取引をいいます。
したがって、完全に廃業している事業は「会社の事業の部類に属する取引」に含まれませんが、一時的に休業している事業は「会社の事業の部類に属する取引」含まれます。
また、事業地域が異なる場合には、原則として「会社の事業の部類に属する取引」に含まれませんが、会社が当該地域への進出を決意し、開業準備行為に着手している場合には、「会社の事業の部類に属する取引」に当たる可能性があります。
1-1-2 在任中の競業行為が判明した場合はどうなるのか?
株主総会(取締役会)の承認を得ずに競業行為を行っていることが判明した場合には、①会社による差止請求や、②損害賠償請求の対象になり(会社法423条1項)、③取締役を解任することの正当な事由があることにもなります(会社法339条1項、2項)。
そのため、在任中における競業行為を検討されている場合には、株主総会(取締役会)の承認を得ることが必須といえます。
会社法423条1項 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法339条1項 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2項 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
1-1-3 利益相反取引にも注意が必要
競業行為同様、株主総会(取締役会)の承認を要する取引としては、取締役が、会社と自身の利益が相反する取引を会社に行わせるとき(これを利益相反取引といいます。)が挙げられます。
利益相反取引については、次の記事で詳しく解説しておりますので、是非ご参照ください。
【よく分かる!取締役の利益相反取引の基本ルール】
【取締役が利益相反取引を行う場合の留意点 完全ガイド】
1-2 退任後
1-2-1 退任にあたって、競業避止義務や営業秘密保持義務の合意書を作成していない場合はどうなるか?
1-2-1-1 競業行為を禁止する合意がなければ、原則として競業行為も可能
退任した取締役に関しては、当然に競業行為が禁止されるわけではありません。
これは、取締役が退任後も生活をしていかなければならず、収入を得るためにどのような職業を選択するかは基本的には個人の自由(職業選択の自由)であり、競業しないことを約束(誓約書、個別の合意書、役員規程等)しているような場合でなければ、競業を禁止するべきではないという発想に基づくものです。
1-2-1-2 合意がなくても、退任した取締役は営業秘密保持義務を負う
他方、営業秘密等に関しては、会社との間で明示的な合意がなくとも、取締役としての善管注意義務・忠実義務(会社法330条、民法644条、会社法355条)に基づき、退任後も一定の範囲で秘密保持義務を負うと解されます(大阪高裁平成6年12月26日判決等)。
大阪高裁平成6年12月26日判決は、会社(「控訴人」)の取締役であった者(「被控訴人」)が、在職中に知り得た秘密情報をもとに取引先に対して営業をかけたとして、会社が元取締役に対して不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。
【大阪高裁平成6年12月26日判決】
「従業員ないし取締役は、労働契約上の付随義務ないし取締役の善管注意義務、忠実義務に基づき、業務上知り得た会社の機密につき、これをみだりに漏洩してはならない義務があることはいうまでもないし、また、《証拠略》によれば、控訴人は、その就業規則中で、従業員に対し、その業務上知り得た機密の漏洩を禁止し(就業規則四条)、これに違反して業務上の秘密を洩らし会社に損害を及ぼしたときは懲戒解雇とする旨を規定(同七四条三号)しているところでもあるが、控訴人には、その知り得た会社の営業秘密について、退職、退任後にわたっての秘密保持や退職、退任後の競業の制限等を定めた規則はないし、従業員ないし取締役が退職、退任する際に、それらの義務を課す特約を交わすようなこともしていない。しかし、そのような定めや特約がない場合であっても、退職、退任による契約関係の終了とともに、営業秘密保持の義務もまつたくなくなるとするのは相当でなく、退職、退任による契約関係の終了後も、信義則上、一定の範囲ではその在職中に知り得た会社の営業秘密をみだりに漏洩してはならない義務をなお引き続き負うものと解するのが相当であるし、従業員ないし取締役であつた者が、これに違反し、不当な対価を取得しあるいは会社に損害を与える目的から競業会社にその営業秘密を開示する等、許される自由競争の限度を超えた不正行為を行うようなときには、その行為は違法性を帯び、不法行為責任を生じさせるものというべきである。」
また、不正競争防止法では、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を「営業秘密」とした上で(同2条6項)、会社の「営業秘密」を「不正の手段により」取得し、使用する行為(同2条1項4号)等を禁止していますので、注意が必要です。
不正競争防止法2条6項 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
不正競争防止法2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
4号 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第六号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。)
5号 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
6号 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
7号 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
8号 その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
9号 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
会社が「秘密として管理」していたのであれば、例えば、顧客名簿も「営業秘密」に該当することになりますし、また、社外持出禁止の顧客名簿を一時的に外に持ち出してコピーしたような場合は勿論、社内で個人所有のパソコンのハードディスク内に情報を入力することまで、「不正の取得」であるとした裁判例もあります(東京地方裁判所平成12年10月31日判決)。
このように、顧客情報の持出しなどについては、たとえ退任時に秘密保持義務の合意をしていなかったとしても、不正競争防止法により制限される場合があるのです。
1-2-2 退任にあたって、競業避止義務や営業秘密保持義務の合意書を作成してしまった場合はどうなるのか?
退任後の競業行為については、当然に禁止されるわけではありませんから、会社側は、競業を禁止する内容の合意書を作成するよう求め、退任後も競業避止義務を課すために交渉してくるでしょう。
また、退任にあたって合意書を作成し、その中で、秘密保持義務の対象となる営業秘密とは具体的に何をいうのか、また、これに違反した場合にはどうなるのかという点を明確にしておく方が、何の合意もない場合よりも、退任した取締役に対する抑止力は強いと考えられます。ですから、会社側は、競業行為の禁止とセットで、秘密保持義務を課す合意書の作成を求めて交渉してくるでしょう。
会社から、そのような合意書の作成を求められた場合、安易に応じてはいけませんが、会社とのパワーバランスで、これを断り切ることができず、合意書を作成してしまった方もいらっしゃると思います。
しかしながら、退任後の競業を禁止したり、秘密保持義務を課したりする合意については、取締役の職業選択の自由にも関わりますので、有効とされる場合も限定されます。どのような場合に合意の有効性を争うことができるのか、競業行為の禁止と営業秘密保持のそれぞれの部分に分けてポイントを解説します。
1-2-2-1 競業避止義務の条項、6つのポイント
退任時に合意書を作成し、競業避止義務を課す条項が盛り込まれている場合には、まず退任後の競業行為は原則として自由であるため、無制限に競業行為を禁止することはできないという点を理解しておく必要があります。
すなわち、合意書を作成してしまったとしても、その内容が退任後の選択肢を過度に狭め、取締役の不利益が大きなものとなっているような場合には、当該合意書に基づく競業避止義務は無効であると判断される可能性が高くなります。競業行為を禁止する条項の有効性を判断するためのポイントは次に挙げる6項目で、裁判例でもこれらの要素が非常に重視されています。
| 【競業行為を禁止する条項の有効性を判断するためのポイント】 ① 営業秘密・取引先維持といった会社側の必要性 ② 取締役が在任時に従事していた地位、業務の内容 ③ 競業行為が禁止される地域的(場所的)な範囲 ④ 競業行為が禁止される期間 ⑤ 禁止される競業行為の範囲 ⑥ 代償措置の有無・内容 |
①は、退職した取締役に競業避止義務を課す必要性があるのか、すなわち会社の正当な利益を守る目的があるのかどうかということです。会社側に機密情報の漏洩や、取引先を奪われることを防止するという正当な目的がないにもかかわらず、競業避止義務が課される場合には、合意が無効であると判断されやすくなります。
②は、例えば、取締役が在任中に顧客情報と接触する可能性がなかった場合に、当該取締役について取引先との接触を禁止することは、あまり合理的ではなく、不必要に過度な制約になってしまいます。そのため、取締役が在任中に従事していた具体的な業務を踏まえ、①の会社が守るべき利益と、⑤の禁止される競業行為との関連性が明確でもないというのであれば、無効な合意であると判断されやすくなります。
③と④は、取締役の自由を過度に制約しないという観点から、会社の目的を達成するために、必要最小限の範囲にすることが求められているものです。③の「地域的(場所的)範囲」に関しては、例えば、会社が営業活動を行っていた地域に限定することなく、広範な競業避止義務を課す場合には、無効な合意であると判断されやすくなります。また、④の「期間」に関しても、6か月や1年、2年といった期間ではなく、5年といった長期間の場合には、無効な合意であると判断されやすくなります。
我々が相談をうける事案でも、例えば、その会社が東京で事業しかしていないにもかかわらず、日本全国での競業行為を禁止したり、10年間の競業を禁止するといった合意がありました。これらの合意は、職業選択の自由を過度に制約するものとして無効になります。
⑤も、取締役の自由を過度に制約するのではなく、会社の正当な利益を守るために、禁止すべき行為は何か、具体的に特定した上で、必要最小限度のものとする必要があります。禁止される行為が抽象的な場合には、結局、何が禁止されているのかよくわからない、禁止の範囲が広すぎるということになるため、無効な合意であると判断されやすくなります。
⑥は、取締役が競業を禁止される結果、転職先が制限されるなど経済的な不利益を被る可能性があることに鑑みて、会社が、取締役の経済的な不利益を補償する配慮をしているかどうかというものです。取締役在任中の報酬や退職金の額が当該不利益を補償するに足りないほど低額である場合には、無効な合意であると判断される方向に働くことになります。
1-2-2-2 営業秘密保持義務のポイント
単に、退任時の合意書において、「会社の営業秘密を使用してはならない」と定められても、それだけでは、結局、何が「営業秘密」に該当するのか全く不明であり、秘密保持義務を負う範囲が不明確となります。
そのため、例えば、取引先に関する情報を利用し、それが会社に発覚してしまったというような場合であっても、取引先に関する情報が「営業秘密」に該当するかどうかは不明といわざるを得ず、裁判において、秘密保持義務の対象となる「営業秘密」に該当しないという判断がなされる可能性もあります。
ですから、何が営業秘密に該当するか、会社側の主張を鵜呑みにする必要はありませんし、明確に特定されていないものなどについては争う余地もあるのです。
営業秘密については、こちらに詳しく書いておりますので、参考にしてみてください。
2-1 在職中
では、在職中の従業員の競業についてはどうでしょうか。
在職中の従業員の場合、会社との信頼関係の上で労働契約を締結し、それが有効に存続している以上、特に個別に合意をせずとも、当然に、営業秘密の保持義務や競業避止義務を負っています。
そのため、個別の合意書を作成していなくても、差止請求等や、非違行為として懲戒処分の対象となってしまいますので(通常、会社の就業規則中に、懲戒事由として「在職中に競業行為を行ったこと」・「許可なく他の会社等の業務に従事したこと」という定めが置かれています。)、注意が必要です。
従業員の兼業については、会社側からの目線でも、次の記事で詳述していますので、是非ご参照ください。
【社員の兼業はどこまで禁止できるか?兼業禁止について経営者が押さえるべきポイント】
2-2 退職後
2-2-1 退職にあたって、競業避止義務や営業秘密保持義務の合意書を作成していない場合はどうなるか?
2-2-1-1 競業行為を禁止する合意がなければ、原則として競業行為も可能
まず、原則として、会社を退職した従業員は、当然に競業避止義務を負うわけではありません。
その根拠は、従業員の職業選択の自由を尊重することにあります。従業員は退職後も生活をしていかなければならず、その糧を得るためにどのような職業を選択するかは基本的には個人の自由であり(職業選択の自由)、競業しないことを自ら約束(誓約書、就業規則、個別の合意書等)しているような場合でなければ、競業を禁止するべきではないという発想に基づくものです。
2-2-1-2 合意がなくても、退職者は営業秘密保持義務を負う
他方、営業秘密等に関しては、退職者との間で明示的な合意がなくとも、労働契約に付随する義務として、退職後も一定の範囲で秘密保持義務を負うと解されています(上記大阪高裁平成6年12月26日判決)。
また、取締役の場合と同様、不正競争防止法により制限される場合もありますので、注意が必要です。
2-2-2 退職にあたって、競業避止義務や営業秘密保持義務の合意書を作成してしまった場合はどうなるのか?
2-2-2-1 競業避止義務の条項、6つのポイント
退職にあたって、もし競業避止義務や営業秘密保持義務の合意書を作成してしまった場合であっても、その内容が、退職後の選択肢を過度に狭め、従業員の不利益が大きなものとなっているような場合には、当該合意に基づく競業避止義務は無効であると判断される可能性が高くなります。
退任した取締役の場合同様、競業行為を禁止する条項の有効性を判断するためのポイントは次に挙げる6項目ですが、従業員の場合、取締役と比較して、地位や業務内容の重要性が低くなってくるでしょうから、無効な合意であると判断される方向に働きやすいといえます。
| 【競業行為を禁止する条項の有効性を判断するためのポイント】 ① 営業秘密・取引先維持といった会社側の必要性 ② 退職者が在職時に従事していた地位、業務の内容 ③ 競業行為が禁止される地域的(場所的)な範囲 ④ 競業行為が禁止される期間 ⑤ 禁止される競業行為の範囲 ⑥ 代償措置の有無・内容 |
東京地方裁判所平成24年1月13日判決は、外資系保険会社の幹部として勤務していた原告が、会社との間で、①競合他社への転職を禁じる内容の競業避止義務を負うこと、②競業避止義務に反した場合には、退職金を不支給とするという合意書を作成していた事案です。
元従業員が競合他社に就職したため、会社は競業避止義務違反があるとして退職金を不支給としました。これに対して、元従業員が会社を被告として退職金の支給を求める訴訟を提起したものです(以下、「原告」とは、競業行為を行った元従業員を、「被告」とは、元従業員が勤務していた会社を指します)。
【東京地方裁判所平成24年1月13日判決】
「本件競業避止条項を本件転職に適用することは公序良俗に反するか否か
(1) 本件競業避止条項を定めた使用者の目的
・・・むしろ本件においては、競合他社への人材流出自体を防ぐこと自体を目的とする趣旨も窺われるところではあるが、かかる目的であるとすれば単に労働者の転職制限を目的とするものであるから、当然正当ではない。
結局、本件競業避止条項を定めた使用者の目的は、正当な利益の保護を図るものとはいえない。
(2) 原告の退職前の地位について
・・・保険商品の営業事業はそもそも透明性が高く秘密性に乏しいし、また、役員会においては、被告の経営上に影響が出るような重要事項については、例えば決算情報が3週間は部外秘とされるといった時限性のある秘密情報はあるが、原告が、それ以上の機密性のある情報に触れる立場にあったものとは認められない。
(3) 競業が禁止される業務の範囲
・・・競業が禁止される業務の範囲については、不明確な部分もあるものの、バンクアシュアランス業務を行う生命保険会社への転職が禁止されていることは明確であった。
しかし、原告の被告において得たノウハウは、バンクアシュアランス業務の営業に関するものが主であり(原告本人)、本件競業避止条項がバンクアシュアランス業務の営業にとどまらず、同業務を行う生命保険会社への転職自体を禁止することは、それまで生命保険会社において勤務してきた原告への転職制限として、広範にすぎるものということができる。
(4) 期間、地域の範囲
・・・保険業界において、転職禁止期間を2年間とすることは、経験の価値を陳腐化するといえるから(原告本人)、期間の長さとして相当とは言い難いし、また、本件競業避止条項に地域の限定が何ら付されていない点も、適切ではない。
(5) 代償措置の有無
原告の賃金は、相当高額であったものの、本件競業避止条項を定めた前後において、賃金額の差はさほどないのであるから、原告の賃金額をもって、本件競業避止条項の代償措置として十分なものが与えられていたということは困難である。」
2-2-2-2 営業秘密保持義務のポイント
秘密保持義務を負う範囲が不明確な合意については、もし取引先に関する情報を利用し、それが会社に発覚してしまったというような場合であっても、取引先に関する情報が「営業秘密」に該当するかどうかは不明といわざるを得ず、裁判において、秘密保持義務の対象となる「営業秘密」に該当しないという判断がなされる可能性もあります。
さらに、合意書において営業秘密が具体的に特定されているかどうかに加え、①当該情報が実際に会社の事業にとって重要であり、かつ従業員が当該情報を外部に漏らすことがないよう秘密情報として社内において管理されていたこと、②秘密保持義務を課される者(退職者)が当該営業秘密の内容を熟知し、その利用方法及び重要性を認識していること、という点も、営業秘密保持義務の有効性判断にあたって重要となってきます。このことは、次の裁判例でも言及されています。
東京地裁平成20年11月26日判決は、従業員が退職するにあたって、「業務上知り得た会社の機密事項、工業所有権、著作権及びノウハウ等の知的所有権は、在職中はもちろん退職後にも他に漏らさない」という誓約書を会社に提出していました。しかし、退職した従業員が、在職中に知った仕入先の情報を使用して、他社で業務を行ったことから、競業避止義務違反及び秘密保持義務違反が問題となった事案です。
【東京地裁平成20年11月26日判決】
「従業員が退職した後においては、その職業選択の自由が保障されるべきであるから、契約上の秘密保持義務の範囲については、その義務を課すのが合理的であるといえる内容に限定して解釈するのが相当であるところ、本件各秘密合意の内容は、上記前提となる事実で認定したとおり、秘密保持の対象となる本件機密事項等についての具体的な定義はなく、その例示すら挙げられておらず、・・・しかも、・・原告の従業員は、本件仕入先情報が外部に漏らすことの許されない営業秘密として保護されていうということを認識できるような状況に置かれていたとはいえないのである」
「このような事情に照らせば、・・・本件仕入先情報が本件機密事項等に該当するとして、それについての秘密保持義務をおわせることは、予測可能性を著しく害し、退職後の行動を不当に制限する効果をもたらすものであって、不合理であるといわざるを得ない。したがって、本件仕入先情報が秘密保持義務の対象となる本件機密事項等に該当すると認めることはできない。」
3 まとめ
取締役の場合も従業員の場合も、考え方としては多くの事項が共通してきますが、あなたが置かれている立場に応じて、ポイントを押さえていくことが重要です。
会社とのトラブルに巻き込まれた方だけではなく、これからビジネスを始めようとしている方も、是非参考にしてみてください。