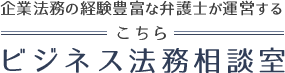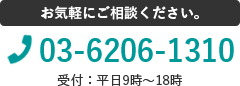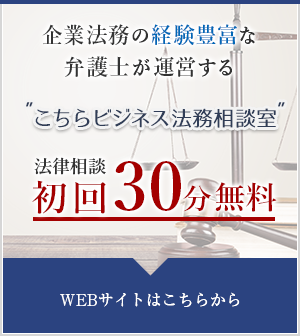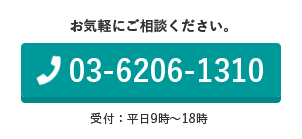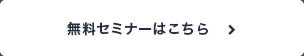業務委託契約とは、端的に言えば、一方の当事者が、何らかの業務を他方当事者に委託する(任せる)契約ですが、システムの開発・保守、製造、運送、警備、経理、コンサルティング等、委託する業務の内容は挙げればきりがないほど、極めて多岐にわたります。
一つの会社が、何種類もの業務委託契約を締結していることも多々あるため、我々弁護士が、業務委託契約を巡るトラブルに関する相談を受ける機会は非常に多いのですが、クライアントの方が「こんなはずではなかった」と後悔するポイントは、いずれも似ていることが多いのです。
すなわち、業務委託契約の種類は様々であっても、業務委託契約に潜む紛争の火種として注意すべきポイントは、多くの契約において共通しているのです。
紛争の火種となりやすい条項は、大きく分けて5つに分類できますが、業務委託契約書の作成・レビューの依頼を受けたときは、まずは、この5つのポイントを確認します。もちろん、わたしたち弁護士が確認すべき点は、この5つに尽きるわけではありませんが、特に注意するべきこれらのポイントを把握していることで、迅速に的確なコメントをすることができるのです。
そのため、最低限、この5つについては十分に理解をしておけば、あなたが業務委託契約の作成、レビュー、交渉等を任されたとき、自社に有利な契約の締結をすることが可能となり、「こんなはずではなかった」という事態を避けることができます。
そこで、典型的な業務委託契約の雛形をベースとして、あなたが業務委託契約書の作成やレビュー、交渉をする際に、注意すべき5つの具体的な条項を中心に解説をしていきます。ぜひ参考にしてください。
2019.9.6 更新
Contents
1、業務委託契約とは? 請負か委任か?
冒頭で、業務委託契約とは、何らかの業務を委託する(任せる)契約であると説明しました。様々な契約について定めた民法には、売買契約や賃貸借契約等、社会生活の中で不可欠な契約に関する条文がありますが、実は、民法の中には「業務委託契約」という言葉はでてきません。
業務委託契約は、その内容によって、民法上の「請負」契約、「委任」契約のいずれかの性質を持つものとして整理されます。この「請負」か「委任」のどちらの性質を持つかによって大きく変わってくることがあります。
「請負」契約とは、一方の当事者が、ある仕事を完成させることを約束し、他方当事者がそれに対して報酬を支払うというものです(民法632条)。典型的なものは、建設会社にビルの建設を頼むような場合であり、この場合、建設会社はビルを完成させないと、報酬をもらうことはできません。「請負」契約の特徴は、仕事の完成が目的となっているというところにあります。
他方、「委任」契約は、一方当事者が、ある事務の処理を他方当事者に委託するという契約です(民法643条、656条)。典型的なものは、弁護士に訴訟の提起を依頼する場合や、医師に手術を依頼する場合が挙げられます。この場合、弁護士も医師も、プロとして求められる注意義務を尽くして業務を遂行する必要がありますが、必ずしも、勝訴あるいは手術の成功という結果が約束されているものではありません。すなわち、「委任」契約では注意義務を尽くして職務を行うことが契約の内容となっているのであり、「請負」契約とは異なり、仕事の完成(勝訴・手術の成功)ができずとも、契約に違反したことにはなりません。
民法632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
業務委託契約は、大きく分けると、仕事の完成を委託する請負型か、事務の処理を委託する委任型かに区別されることになります。
例えば、システムの開発業務を委託する契約であれば、必要な注意義務を果たしたというだけでは足りず、完全なシステムの構築が求められているのであって、請負型ということができます。他方、警備会社にビルの警備の業務を委託するような契約であれば、警備業者としては、必要な注意義務を果たして警備業務を遂行すれば足り、そこに、仕事の完成という概念は入りません。
このような区別は、後に述べるように、業務を受託する側が何をすれば報酬を請求できるかという最も重大な点にかかわってきます。
また、細かい点ではありますが、請負型の業務委託契約であれば、印紙税法に基づき、契約書に印紙を貼る必要がある一方、委任型の場合には、印紙は不要というような違いもあります。
まず、あなたが締結しようとしている業務委託契約が、仕事の完成を目的とする請負型か、そうではなく委任型のいずれであるかという視点を持ちましょう。
2、具体的なポイント解説
次からは、業務委託契約の雛形を用いて、具体的な条文ごとにポイントの解説をします。この雛形では、仕事の完成ではなく、事務の処理を委託する委任型を想定していますが、適宜、請負型についても言及をしたいと思います。
2-1 ポイント① 委託業務の内容に関する定め(1条)
業務委託契約をめぐるトラブルで最も多いのが、業務を委託した側からは、「依頼したはずの業務なのに、別料金と言われた!」、業務を受託した側からは、「それは委託業務の内容に入っていない!」というものです。すなわち、何を委託したのか、契約書上明らかになっておらず、当事者間の認識に齟齬があることで、起こるトラブルです。
そのため、当たり前ですが、請負型にせよ委任型にせよ、業務委託契約書を作成する際にもっとも重要なのは、いかなる業務を委託するかを、具体的に特定して記載することです。
委任型であっても、委託された事務を処理して初めて、受託者は報酬を請求でます。
事務の処理がポイントとなる委任型、例えば、コンサルティング業務の委託契約であれば、月ごとの会議の回数、コンサルタントが行う調査の手順・方法、コンサルタントからの報告書に記載すべき項目・提出頻度や時期、業務に従事するコンサルタントの人数など、可能な限り詳細かつ具体的に特定しておかなければなりません。
仕事の完成がポイントとなる請負型、例えば、システム開発の委託であれば、いかなるシステムの開発なのか、契約書において仕様書を引用して細部まで取り決め、これをいつまでに完成させるのか(納期)を明らかにしておく必要があります。また、これが完成した場合の検収の手順についても定めておく必要があります。
2-2 ポイント② 業務委託料(報酬)に関する定め(3条)
業務委託契約を巡る典型的なトラブルの2番目は、業務委託料の支払に関するものです。これは、2-1で述べたいかなる業務を委託しているかと密接に関連しますが、「何をすれば」、また、「いつ」、業務委託料(報酬)を請求することができるかが、契約書上明らかになっていないことから起こるトラブルです。
そのため、これも当たり前ですが、「いかなる業務を完成(又は処理)すれば」、「どのような条件をクリアすれば」(委託者の検収を経る等)、「いつ」(検収完了後10日以内等)など、業務委託料(報酬)の支払に関して、当事者間で認識の齟齬が生じないように、契約書に具体的に記載しておく必要があります。
委任型の場合には、委託した事務の処理がなされていることを前提に、毎月の支払時期を明記した上で月額●円、あるいは、成果報酬がある場合にはその算定方式を記載するという定め方がされる場合が通常だと思われます。
他方、請負型の場合には、完成物を納品し(あるいは、受託した業務を完遂し)、これについて研修が完了した段階で一括して代金を支払うというのが通常だと思われます。
2-3 ポイント③ 有効期間・中途解約に関する定め(5条・6条)
2-3-1 契約の終了に関するトラブル
次に典型的なトラブルは、業務を委託してみたものの、パフォーマンスに不満があるので、契約を解約しようとしたところ、違約金等の支払を請求されたというような、中途解約に関するものです。
これは、中途解約が可能かどうか、可能である場合にはその条件等について、具体的に契約書に記載がなかったことが原因ですが、どのように交渉すべきだったのでしょうか。
まずは、業務委託契約に有効期間に関する条項がある場合の原則からみていきましょう。
2-3-2 有効期間
業務委託契約の場合、システムの開発業務委託のような、完成したシステムを納品するという一回きりで終わる請負型の契約もありますが、一定期間、業務の提供を継続するという形の契約となることが多いと思います。
その場合は、契約において、有効期間を定めた上で、自動更新条項が定められることが一般的です。雛形の5条2項はこの自動更新条項を定めたものです。
2-3-3 中途解約の条項
有効期間のある業務委託契約の場合、原則として、期間が満了するまで契約を終了させることはできません。しかし、冒頭で述べたように、例えば、コンサルティング契約において、コンサルタントは一生懸命やってくれているものの、期待していたほどのパフォーマンスではないという場合、途中で契約を終了したいという場合があります。
このような場合に備えて、業務を委託する側としては、中途解約の条項を定めておく必要があります。
業務を委託をする側としては、特にペナルティなく、いつでも自由に中途解約をすることができるという内容がベストです。
他方、業務を受託する側としては、中途解約がされた場合には、見込んでいた業務委託料(報酬)が中途解約によりもらえなくなるわけですから、その補償、すなわち、残りの期間分の業務委託料(報酬)の支払いを受けられるという内容がベストということになります。
中途解約の場面では、このように、依頼をする側・受ける側の利益が対立するわけですが、雛形6条では、一つの落とし処として、双方の利益に配慮した以下の定め方をご紹介しています。
- 中途解約をするには、例えば「3か月前」等、あらかじめ定めた期間を置いて事前に通知し、通知をしてからその期間が経過して初めて、中途解約の効力が生じる。
- ただし、依頼をする側が、あらかじめ定めた期間分(「3か月分」等)の業務委託料(報酬)分を支払えば、事前に通知をしなくても即時に解約ができる。
請負型の場合には、2-2で述べたとおり、仕事の完成時に代金を一括で支払うという定め方がされるのが通常です。
もっとも、いったん仕事をお願いしたものの、完成前に不要になったので解約をしたいという場合もあり得ます。このような場合には、契約書に特に明記していなければ、以下の民法641条が適用されます。すなわち、注文者(仕事を依頼した側)は、いつでも契約を即時解除することができるものの、損害の賠償をしなければならないことになります。
民法641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
「損害を賠償」とは、本来の業務委託料(報酬)を支払わなければならないということですが、そうすると、注文者(仕事を依頼した側)としては負担が大きすぎる場合があり得ます。そのような事態を想定して、注文者(仕事を依頼した側)としては、例えば、損害賠償の範囲を、実際に業務に従事した日数で日割りした金額にする、中途解約までの完成度の割合に応じて業務委託料(報酬)を支払う、というような定め方をすることが考えられます。
2-4 ポイント④ 再委託の禁止(7条)
4つめの典型的なトラブルは、あなたの会社はA社との間で業務委託契約を締結し、A社に対して業務を委託していたのに、A社は下請けのB社に業務の遂行を丸投げをしていたというものです。
業務を委託する側としては、通常は、その業務委託先(A社)を信頼して依頼をするわけですから、一般的には、業務委託先(A社)が、当該業務の全部又は一部を第三者(B社)に再委託(丸投げ)することは想定されてない場合が多いと思われます。
そうであれば、予めそのことを契約書に定めておく必要があります。
雛形7条1項では、原則として、再委託をすることはできないとし、仕事を依頼する側が事前に書面により承諾をした場合に限って、再委託を許すという建付けとしています。
なお、個人情報の取扱いに関する業務を委託するような場合、仕事を委託する側は、業務委託先に対する「必要かつ適切な監督」を行う必要があります(個人情報の保護に関する法律22条)。
そのため、業務委託先(A社)が下請け(B社)に当該業務を再委託することが想定されている場合は、仕事を依頼する側(あなたの会社)としては、再委託先の選定(B社が)にも十分に注意を払う必要があります。この場合、雛形7条のように、再委託を原則として禁止し、例外的に、事前に審査をして書面により承諾をした場合に限り再委託を認めるという条項が必須となります。
個人情報の保護に関する法律22条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2-5 ポイント⑤ 損害賠償の請求(10条)
最後に、業務委託契約を巡るトラブルの典型例として、損害賠償の請求について解説をします。
例えば、あなたの会社がA社と業務委託契約を締結して、A社に対してシステムの提供をしていたところ、システムの不具合が生じ、これによりA社に莫大な損害が発生したため、A社から損害賠償請求を求められたというような事例を想定してください。
故意又は過失により、契約上の義務に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対して損害賠償をする義務があります。これ自体は、契約書において特に定めずとも、民法の規定に基づいて当然に認められるものですが、雛形10条では注意的にこれを定めるものです。
そのため、あなたの会社はシステムを提供することで、毎月固定の業務委託料(報酬)を受領していたとしても、契約書に特に定めておかなければ、その報酬額を大きく上回る損害賠償請求をされるリスクがあるのです。
ここで、そのようなリスクを避けるために、システムの提供等、業務を受託した側として、ぜひ入れておきたいのは、損害賠償の上限を置くための条項です。
実際に莫大な損害が発生したとしても、予め合意した範囲でしか賠償責任を負わないという損害賠償の上限額を定めておく条項は、何かあった場合の損害賠償の範囲の予測が難しい場合によく用いられます。
以下の条項は、この賠償額の予定を定め、具体的には、この6か月分の業務委託料(報酬)の金額を上限とする内容としています。
- 第10条(損害賠償の請求)
甲又は乙が、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対してその損害の賠償をしなければならない。ただし、かかる損害賠償請求の金額は、6月分の業務委託料を上限とする。
他方、業務の提供をする側が、このような条項を入れることを希望しても、相手方が受け容れないという場合もよくあります。その場合には、「故意又は重大な過失の場合」は除く(通常の損害賠償のルールで解決する)という定め方に落ち着く場合が多いように思います。
- 第10条(損害賠償の請求)
甲又は乙が、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対してその損害の賠償をしなければならない。ただし、本契約の違反が故意又は重大な過失による場合を除き、かかる損害賠償請求の金額は、6月分の業務委託料を上限とする。