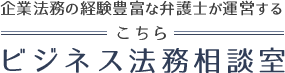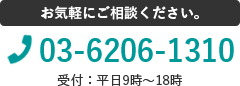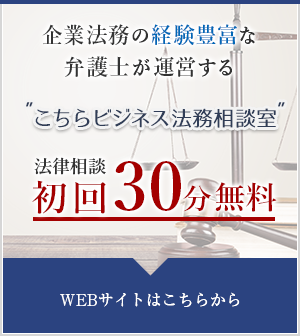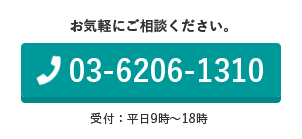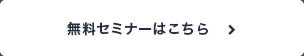中小企業においては、例えば一時的な業績不振時の対応として将来入金予定の売掛金を譲渡することで現金化して事業資金に回すなど、債権譲渡の手法が多く用いられています。
また、取引先に対して一定の支払サイトを設けた取引(掛け取引)を行う際に、当該取引先が有する売掛金等の債権を担保(譲渡担保)に取ることで、万が一、当該取引先から支払いが受けられなくなった場合に備えることも広く行われています(債権譲渡担保については、次の記事もご参照ください)。
参照:【ひな形あり】取引先の債権を担保にとる方法【債権譲渡担保】
特に、かつては債権譲渡(譲渡担保を含む。)を対抗するためには譲渡債権の債務者(取引先など)への通知等が必須とされていたところ、平成10年10月に施行された債権譲渡特例法により、この通知等に代わり債権譲渡を登記することで対抗要件を備えることが可能となったことを受け、債権譲渡ないし債権譲渡担保がより有効活用されるようになりました。
もっとも、譲渡される債権の債務者にとっては、弁済をすべき相手が変わってしまうこととなり、誰に弁済すべきか分からなくなるなどのデメリットもあることから、契約書において、債権譲渡を禁止する特約(旧法時代には「譲渡禁止特約」と呼ばれていましたが、改正法では「譲渡制限特約」と呼ばれます。)を設けることが多くあります。
そこで、改正後民法においていは、譲渡禁止特約の取り扱いについて改正が食われてられております。
本稿では、この譲渡制限特約の効力について解説します。
なお、改正後民法の適用を受けるのは、令和2年4月1日以降に債権譲渡がなされた場合です。それ以前に債権譲渡や債権譲渡登記がされた場合には、改正前民法が適用されますので、ご注意ください。
1 譲渡制限特約の効力
改正前民法では、債権について譲渡禁止特約がある場合には、債権譲渡は原則として無効とされておりました。
債権譲渡特約とは、契約において、債権の譲渡を禁止する条項がある場合などです。
これに対し、改正後民法では、譲渡制限特約がなされた場合であっても債権譲渡は有効となります(民法466条2項)。これは、改正前の民法においては、譲渡禁止特約のある債権譲渡を無効とされていたことと真逆の結論に変更されています。
もっとも、これでは譲渡制限特約を結んだ債務者の利益が保護されないことから、次のとおり一定の配慮がなされています。
第466条(債権の譲渡性)1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。3,4(省略)
2 債務者の抗弁
譲渡制限特約を付した債務者を保護するため、債務者は、譲渡制限特約に悪意又は重過失の譲受人等(質権者等を含む)に対しては、債務の履行を拒むことができ、かつ、債権の譲渡人に対して弁済等を行った場合には、債務消滅の効果を譲受人等にも主張することができるとされています(民法466条3項)。
つまり、債務者は、譲渡制限特約について悪意・重過失の譲受人等から請求を受けても支払いを拒否し、もともと債権者であった譲渡人に対して支払うことができます。
他方、譲渡人は、既に債権を譲渡している以上、債務者に対して支払いを請求することはできず、債務者が譲受人に対する支払いを拒否して譲渡人への支払を選択した場合にのみ、弁済を受けられることとなります。
第466条(債権の譲渡性)
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
3 履行催告権
上記2のルールにより、債務者は、債権の譲受人に対しては譲渡制限特約の存在を主張して支払を拒み、譲渡人に対しても既に債権を譲渡したことを理由に支払を拒むことが可能となるため、事実上、譲渡人も譲受人も請求できない「デッドロック状態」が生じてしまいます。
このような状態を解消するため、債権の譲受人は、債務者に対し、相当の期間を定めて譲渡人に支払うよう催告し、期間内に支払われないときには、債務者は上記2の抗弁を主張できなくなる(=債権の譲受人に支払わなければならなくなる)こととされました(民法466条4項)。
第466条(債権の譲渡性)
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
4 債務者による供託
譲渡制限特約を付した債権が譲渡されてしまった場合、債務者は、当該債権譲渡が有効であることを前提に譲受人に対して支払うこともできますし、譲受人が譲渡制限特約につき悪意・重過失があるとして譲渡人に対して支払うこともできます。
もっとも、譲受人に悪意・重過失があると考えて譲渡人へ支払ったところ、後にこれが善意ないし無重過失であったと判明した場合、債務者は、譲受人からも再び支払いを求められるリスクがあります。このような債務者の不利益に配慮して、譲渡制限特約付債権が譲渡された場合には、債務者は供託することが可能とされました(民法466条の2第1項)。
これまでも、我々の下に、債権譲渡通知を受けた取引先からその対応方法について相談を受けることがあり、二重弁済のリスクがあるため、供託をアドバイスすることが多くありました。
改正後民法では、条文上、供託できることが明らかになっていますので、どちらに支払って良いか不明な場合には、供託をすることをお勧めします。
この供託金の還付請求は、譲受人のみが可能とされています(同上3項)。
第466条の2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
1 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3 第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
また、譲渡制限付債権が譲渡された後に、譲渡人が破産した場合には、その譲受人は債務者に対し、譲渡人の破産管財人に支払わず、法務局に供託するように請求することができます(民法466 条の 3)。
債権を担保に借入をする事業者というのは、金融機関からの借入れもできず、資金繰りに窮している会社が多いです。このような会社に対し、債権を担保に取り、貸付けをした後に、破産をした場合、破産をした会社の破産管財人との間で、その債権をどちらが回収するかについて争いが生じることがありました。
本条項は、破産管財人よりも、譲受人が受け取ることを明確にしたものです。
第466条の3
1 前条第1項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。